その気配には、確かに覚えがあった――力強く、誰よりも頼りにしていた、絶対的に己を護ってくれる存在!!
「父上――!!」
反射的に叫んでいたイポーリトを、一瞬、影は僅かに振り向き、その切れ長の目を微笑ませた。
(――イポーリト!)
「父上!!!」
イポーリトが恍惚と大きく顔を輝かせた時には、トゥパク・アマルの姿をした影は、その強靭な手に握っていた黄金の笏杖を、目にもとまらぬ速さで水平に振り切った。
闇を圧倒して燦然と輝き渡る笏杖が、ほぼ360度の弧を猛然と描き、黄金色の軌跡を宙に引く。
と同時に、その軌跡上にいた十名近くの敵兵が、まとめて一気に中空に弾き飛ばされた。
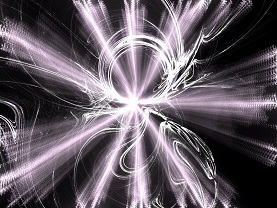
まるで巨人の手によって小人が薙ぎ払われたかのように、敵兵たちは凄まじい勢いで数メートル先まで叩き飛ばされ、そのまま地に激しく全身を打ちつける。
その強度の衝撃と鎧の重さにまごつき体勢を整えきれぬ間に、周囲のインカ兵たちが、この時とばかりに襲いかかって一気に止めを刺した。
一方、イポーリトは、目の前で展開された一連の光景に、息することさえ忘れて釘付けられていた。
が、ハッと我に返って、急いで周囲を見渡す。
「父上!!」
しかし、その時には、彼の目の前からトゥパク・アマルの姿は消えていた。
その代わり、笏杖を手にしたベルムデスが、彼もまた恍惚たる様子でそこに立っている。
イポーリトは懸命に辺りを見渡しながら、汗と血にまみれた瞼をこすった。
(ベルムデスを父上と見間違えた……?!
でも、あんなにハッキリと見えたのに…!!)
父がこのような場所にいるはずはないと、彼の理性はよく分かっているはずだった。
だが、彼の全身には、力強くも温かな感覚が、まばゆい残光のように熱くめぐっていた。
その感覚は、確かに父は己の傍にいて護ってくれたに違いないと、不思議なほどに強い確信を抱かせるものだった。
イポーリトは、右腕に結び付けられた漆黒の布をギュッと握り締める。
(父上!!
たとえ幻だって…父上は今も僕らの傍にいて、一緒に戦ってくれている!!)
「――……!」
呆然と己の手にある笏杖を見つめる。
いっそう暗さを増す闇の中でさえ、笏杖はその神々しい黄金色の光をますます強めているように見える。
笏杖を振るったベルムデス自身にしか分かりようのないことであったが、先の一瞬、己が笏杖を振るったというよりも、明らかに笏杖自身が、自らの意志をもって敵に向かっていったように思えてならなかったのだ。
ベルムデスは、イポーリトの方へと視線を馳せる。
右腕に結ばれた父トゥパク・アマルの布を堅く握り締めながら、恍惚と息を詰めている皇子のシルエットに、ベルムデスもまた確信を深めた。
(トゥパク・アマル様…!
あなた様は、御身は遠く離れていらしても、皇子や我らをしかと護ろうとしてくださっておるのですな)
いつしか引き寄せられるように互いの顔を見合わせていたイポーリトとベルムデスは、瞳で強く頷き合った。

が、そのような二人も、すぐに怒号叫喚のどよめく現実へと意識を引き戻される。
顔を上げると、いつしかまた離れ離れになっていたオルティスが、イポーリトの方へ戻る道を拓こうと、怒涛の格闘を続けているところであった。
その凄腕ゆえに、彼は今や皇子のイポーリトにも等しいほどに敵の標的にされていた。
彼を目がけて続々と攻めかかりくる人群れを、夜闇の中でも真っ赤にてらつく半月刀を振るって斬り伏せながら、懸命にこちらに進んで来ようとしている。
切りが無く湧き出してくる敵兵たちに、あの冷静なはずのオルティスもいきり立っているらしく、怒声を発する声が響きくる。
「まだ来るか…――くそっ!」
オルティスは俊敏に身を翻して敵の突きをかわし、と同時に、目の前に迫り来る無数の剣先を荒々しく薙ぎ払う。
鼓膜を突き刺す金属音が宙に鳴り渡り、闇の中に激しく火花が飛び散った。
そうしながらも、獰猛な剣の林の中を、確実に皇子の元へと押し進んで来る。
「イポーリト様!」
「オルティス!!」
あまりに夥しい返り血で互いの姿も判別しがたいほどであったが、それでも、合流を果たした二人は、双方の健在を確認し合うように、ガシッと力強く剣と刀を交し合った。

それから、オルティスが先刻と同じ言葉を繰り返す。
「イポーリト様、本陣に急がねばなりません!」
「分かってる……!」
イポーリトとて、即座に母や弟たちの残る本陣へ馳せ参じたい気持ちは山々だったが、戦場の激しい攻防の中で、思うように前進させてもらうことができないのだ。
そうしている間にも、周り中では無数の兵たちが戦い、喚き、剣や槍や戦斧が死に物狂いで翻り、うねり続けている。
戦場はすっかり夜の闇の呑まれ、凍てつく冷風に煽られる樹木の梢が、降り注ぐ月光を白々と照り返している。
戦場を囲む霊峰たちの峻厳な山肌も、濃さを増す闇の中で、水墨画のように幻想的な灰黒色に染まりゆく。
今も、インカ軍、スペイン軍、共によく奮戦しており、それ故、両軍の力は拮抗し、互いにとって戦いの時間は永遠にも思われるほど長かった。
終始、辺りで湧き上がる悲鳴や喚声、剣や鈍器のぶつかり合う響き、断片的に弾ける銃声、それらの渦巻く白兵戦の狂気に、イポーリトの体は完全にフラフラだった。
だが、歯を食い縛って彼は剣を振るい続ける。
(また僕が隙を見せたら、さっき一度に多くの兵に襲いかかられたみたいに、もっと敵は攻め上げてくる…!)
それに、あの時、父トゥパク・アマルに助けられた、確かに会えたのだ!!――その鮮烈な実感は、イポーリトに大きな力を与えてくれていた。

しかし、どれほど精神的には奮い立とうとも、体力の限界を超えている体は、そう長くは言うことを聞いてはくれなかった。
視界の悪い闇の中で夜露に濡れた草に足をとられ、不意に体幹のバランスを崩しかける。
その一瞬を逃さず、周囲の敵兵たちが、イポーリトの方へ覆いかぶさるようにして、一斉に襲いかかってきた。
敵兵たちの汗と血の混ざった体臭が、ブワッと、彼の顔に吹きかかった。
イポーリトの中に、嗚咽と共に真っ暗な感覚が腹部の奥から突き上げる。
が、それと同時に、遠くなった耳の奥で、既に聞き慣れたあの半月刀が、頭上で大きく風を切る音がした。
敵兵たちの絶叫に、夜の冷気が引き裂かれる。
それでも、まだ襲い来る剣を相手に、オルティスはいよいよ殺気立った眼を血走らせ、同様に呪い狂った眼光の敵兵たちの胴体を甲冑ごと叩き割っていく。
だが、オルティスの刀をかいくぐった敵兵が、今度はイポーリトの足をめがけて発砲してきた。
空気を切り裂くような発砲音が、至近距離を掠め去る。
濃い闇が辛うじて敵の狙いを妨げ、銃弾は少年の足を僅かにそれ、傍の地面に突き刺さった。
足の自由を奪って己を捕らえようとしているのだという、その敵の露骨な意図が、イポーリトの神経を激しく逆撫でた。
(ここまで来て…そうはさせるか!!)
しかし、皇子が反撃に転ずるより早く、相手の背面首筋一点をめがけたオルティスの肘鉄が、背後から強烈に振り下ろされた。
意識を失った敵兵がドゥッと腹這いに倒れ込む。
が、またもや別の敵兵が、今度はイポーリトの頭部に向かって剣を振り上げた。
反射的に頭を下げると、すぐ上で相手の剣が猛烈な勢いで宙を斬り、同時に、相手の荒々しい息がイポーリトの頭頂に吹きかかる。
「……――!!」
頭上をよぎっていったその振りの鋭さと勢いは、己を生け捕りにしようなどという生半可なものではなく、完全に命を狙っていたものだと分かる強烈な激しさと殺意を孕んでいた。
イポーリトは涸れ果てた喉をひくつかせる。
この期に至っては、もはや敵軍は、自分や母を捕縛することに固執するのをやめて、命を奪おうが殲滅させる方針に変えたのか?
彼は、己の総身を、言いようの無い悪寒が駆け抜けるのを感じた。
その間にも、即座にオルティスの重い半月刀が追いついてきて、イポーリトの頭を襲った敵兵の首筋を背後から薙ぎつけ、叫び声ひとつ立てる隙も与えず斬り伏せた。
全身に受けた返り血のために闇の中に赤黒く浮き上がって見えるオルティスが、イポーリトを振り返る。
その表情は勇ましくも、深い苦渋の影を帯びている。
「イポーリト様、今、本陣からの報告が…!
ガルベス大佐が、ついに彼の直属部隊と共に断崖壁を攻め上り、ミカエラ様の本陣へ侵入を開始しております。
部隊前方に布陣する味方の兵たちが援護に向かっておりますが、我らも一刻も早く本陣へ!!」

オルティスの言葉に、イポーリトの心は凍りついた。
懸命に道を斬り拓き、必死で進んで来たにもかかわらず、本陣への道程は、まだ遥かに遠かった。
だというのに、ガルベスが既に本陣に雪崩れ込み始めているのだとしたら――!
「もう、とても助けには間に合わない……!!」
真っ暗な闇の中でもハッキリと分かるほどに、みるみる蒼白になっていく皇子の肩を、オルティスの手が力強く支えた。
「最後まで諦めてはなりません!
さあ、一刻も早く急ぎましょう!!」
涙の込み上げそうになるのを必死に堪え、イポーリトは頷いた。
その時、後方から、味方のものとも敵のものともつかぬ、大きなどよめきが上がった。
本陣への道を斬り拓き続けながらも、イポーリトやオルティスの意識もそちらに走る。
怒号の戦乱の中では、どよめく兵たちの声も遠く切れ切れにしか聞こえない。
だというのに、イポーリトの耳は、まるで戦場のあらゆる他の音はどこかの異次元に消え去ってしまったかのように、ただ一つの言葉をはっきりと聴き取っていた。
「援軍だ!!
援軍が到着したぞ!!」

イポーリトの心臓が大きく跳ね上がった。
援軍?!――どよめく兵たちは、確かに、そう叫んでいる!!!
その瞬間、過酷な白兵戦の中を生き延びてきた両軍の全ての兵たちの間から、強度の歓喜と戦慄のオーラが共に沸き立った。
「援軍?!
どちらの援軍だ?!」
闇の中で両軍の兵が口々に叫び合う中、イポーリトも、オルティスさえも、その一瞬は本陣へと逸る切迫感を忘れて、強い恍惚と緊張に息を詰めた。
思い余って、イポーリトはオルティスの腕を強く掴んで揺すりながら、相手の目を大きく覗き込む。
「やっぱり父上が、この周辺の地域から兵を集めて、援軍を派兵してくれたんだ!!」
今までの憔悴しきっていた彼とは別人のように、生気に満ちた輝く瞳で己を見上げるイポーリトを見つめながら、しかし、逆にオルティスは不穏な念に憑かれていた。
彼は、これまで常に本陣にあって、国中に散らばるインカ軍の布陣について、かなり正確に把握していた。
その己の記憶が正しければ、戦線が急速に全国的に拡大し、しかも、英国艦隊との決戦を目前に控え、クスコ戦も同時進行している今、いかにトゥパク・アマルとて、即座に当地に派兵できるようなインカ軍の予備兵力は無いはずだ。
この地の周辺部に残されていた兵とて、今はディエゴのクスコ戦に総動員されているはずである。

オルティスは嫌な予感を内に秘めたまま、つとめて沈着な声音でイポーリトを促した。
「イポーリト様、まだ援軍は、我が軍の味方かスペイン側かも分かりません。
敵が浮き足立っている今こそ、我らは、急ぎミカエラ様の本陣へと急ぎましょう」
「あ…ああ、そうだな」
オルティスの言葉に、イポーリトは懸命に意識を前方に戻そうとする。
だが、激しく昂ぶる気持ちをどうにも抑えることができなかった。
(援軍の規模がどれほどか分からないけれど、完全に勢力が拮抗している今、劣勢の中ここまで踏ん張ってこられたインカ軍なら、援軍が加わってくれれば、きっと勝てる!!)
しかし、そのようなイポーリトの希望も、すぐに無残に打ち砕かれた。
「援軍到来」の喚声が上がった直後、速攻、偵察に走ったオルティス配下の斥候たち数名が、伝言をリレーするようにして、「援軍」に関する情報を送ってきたのだ。
鋼鉄の甲冑に身を固めた白人兵たち、剣と銃と大砲による重装備、そして、彼らの間に翻る多数のスペイン軍旗――それらの報告を耳にするオルティスの表情は、険しさを増していく。
それに追い討ちをかけるがごとくに、先刻どよめきの起こった方角から、スペイン軍の歓声とインカ兵の悲痛な叫びとが、ほぼ同時に響き渡ってきた。
「スペイン軍だ!!
スペイン軍の援軍だ――!!」

その瞬間、戦場の空気は真っ二つに割れた。
狂気乱舞せんばかりに、躍り上がって歓呼の雄叫びを上げるスペイン兵たち。
他方、インカ兵たちは絶望に打ちひしがれて、生き残っている者たちさえも、その一瞬に屍と化したかのように萎え果てていく。
そして、イポーリトもまた、身も心も慄然と凍りついていた。
その脇にいるオルティスさえも、その顔色はみるみる蒼白になっていく。
彼自身も胸の凍る思いで、横を走っていたイポーリトに目をやれば、少年は足元もおぼつかぬまま呆然として、今にもサーベルを指先から零れ落としそうになっている。
オルティスはイポーリトの手を取ると、その指に強くサーベルを握り締めさせた。
周囲でますます勢いづいている敵兵たちに鋭い眼光を走らせ、片手で応戦しながらも、オルティスは、もう一方の手で皇子の肩を力強く握り締めた。
イポーリトは力なく首をうなだれ、今、その手に握らされたサーベルさえも、また取り零しそうになっている。
「イポーリト様、しっかりしてください!!」
オルティスは少年の肩を強く揺すった。
「我らは既にここまで、約半数という劣勢にもかかわらず戦い抜いてきたではありませんか!
今さら、敵に多少の援軍が加わったからといって、どれほどのことがありましょう。
さあ、皇子、お顔を上げてください。
今こそ、我が軍には、あなたの力が必要なのです!!」
「オルティス……」
何か応えようと少年の唇が動きかけたが、それよりも先に、力無く上げたその顔に降り積もった戦塵と血痕の上を、ツッと涙が流れ落ちた。
体からは完全に力が抜け落ちてしまっており、今にも崩れてしまいそうに見える。
魂の抜けた虚ろな目でこちらを見上げるその手から、再びサーベルが地へと滑り落ちた。
大人の己でさえも殆ど限界に達している今、まだ少年のイポーリトが、どれほど消耗し、打ちひしがれているか、オルティスには痛いほど察することができた。
しかし、彼は、心を鬼にして、険しい眼で皇子を見据えた。
「イポーリト様、ここでトゥパク・アマル様の御意志を断ち切っても良いのですか?
この反乱のために、どれほど多くのインカの民が命を捧げてきたのか、皇子が一番よく知っているはずです!
トゥパク・アマル様や全ての民の思いや賭けてきた命も、あなたは、今、ここで全てドブに捨て去ると言うのですか?!」

オルティスの言葉に、ますます込み上げる涙で頬を洗いながら、イポーリトは血の滲んだ唇をきつく噛み締めた。
また一人、敵兵を激しく薙ぎつけ、オルティスはイポーリトの腕に結び付けられた漆黒の布をガッシリと握り締める。
そして、素早く皇子のサーベルを拾い上げ、相手の前にそれを掲げ上げた。
「さあ、皇子、剣を!!
大丈夫です!
あなたには、父上がついていらっしゃる。
最後まで諦めてはなりません!
あなたが戦い続ければ、必ず、兵たちもついて参りましょう!!
さあ、皇子!!」
そう言って、オルティスはサーベルを少年の指に絡ませ、力を与えるように、さらに強くその手を握り締めると、相手の胸元にサーベルを構えさせた。
「オ…ル…ティス……」
イポーリトは砕けるほど奥歯を喰い縛ったまま、止まらぬ涙をいよいよ溢れさせるばかりである。
それでも、オルティスは皇子の瞳に幾度も頷きながら、周囲に大きく視線を馳せた。
「イポーリト様!!
兵たちは、皆、あなたの姿に救いを見出そうとしているのです。
あなたが諦めぬ限り、兵たちも、どこまでもあなたについて参ります!!」
いよいよ勢いを増す敵兵たちが猛り狂って殺到してくる中、オルティスの重い半月刀が、続々と群がり来る彼らの胴体を複数同時に斬り伏せていく。
その瞬間、地に沈む敵兵の屍の向こうに、今も必死に戦っているインカ兵たちの姿がイポーリトの瞳の中に飛び込んできた。
しかし、勢いに乗る敵軍の前で、インカ兵は確実にその力をそがれていく。
涙に霞む視界の中で、一人、また一人と、方々で次々と討ち取られていく味方の兵たち。
刹那、倒れゆく一人の兵と目が合ったように思えて、イポーリトの凍てついた心がさらに凍りついた。
倒れゆく兵の目は、役目を果たせず申し訳ありませんと、インカ軍を頼みますと、懸命に己に訴えている…――!
いや、その声無き声は、その兵からだけでなく、己を取り巻くあらゆる方向から流れ込んできているのではないのか?!
いつしか大きく息を詰め、無意識のうちに心眼と心耳を澄ませば、戦場は、無念の声、懺悔の声、そして、それでもなお一縷の希望を己に託そうとする声無き声に満ちている……!!
怒涛のような悲愴と怒気と、そして、奥底から突き上げる雷光のようなものが、突如、イポーリトの全身を電流のように駆け巡った。

「敵軍の援軍」という声を聴いたあの瞬間から、絶望に打ちひしがれ、遮断されてしまっていたイポーリトの心が、重い軋み音を上げながら、今再び、その歯車を回し始める。
と同時に、先刻のオルティスの言葉が、今になって、やっと彼の心の中に流れ込んできた。
『イポーリト様、ここでトゥパク・アマル様の御意志を断ち切っても良いのですか?
この反乱のために、どれほど多くのインカの民が命を捧げてきたのか、皇子が一番よく知っているはずです!
トゥパク・アマル様や全ての民の思いや賭けてきた命も、あなたは、今、ここで全てドブに捨て去ると言うのですか?!』
怒号叫喚のどよめくさなかで、己の手の中にあるサーベルの感触が急速に甦る。
「オルティス!!」
耳を貫いて決然と響き渡ってきた声にオルティスが振り向けば、強い光を取り戻した瞳のイポーリトが、あのトゥパク・アマルに似た面差しで真直ぐに己を見つめている。
その表情に、己の言葉が伝わったのだと悟ったオルティスは、相手の方へ頷き、微笑んだ。
だが、その一瞬の隙だった。
オルティスの心臓を狙った敵の銃弾が夜の大気を切り裂き、殺意に満ちた発砲音が彼の鼓膜を奮わせた。
驚異的な反射神経で、彼はギリギリその身をかわした。
が、その瞬間を狙っていたかのように、彼の右後方で待ち構えていた敵兵の大振りの剣先が滑(ぬめ)るように一閃し、銃弾をよけて身を傾けたオルティスの右上腕めがけて猛然と振り下ろされた。
「オルティス――!!!」
衝撃に張り裂けんばかりに見開かれた少年の目の前で、まるで木に斧を打ち込まれたかのようにバックリ裂けたオルティスの右腕から、大量の鮮血がドッと溢れ出す。

絶叫しながらイポーリトが走り寄ろうとした時には、仁王のごとき激烈な形相と化したオルティスが、己を斬りつけた敵兵を渾身の力で蹴り飛ばし、即座に左に持ち替えた刀で報復の斬撃を見舞っていた。
そして、駆け寄ってきた皇子を見据え、毅然と言う。
「なに、これしきのこと、何ということはありません。
右手が駄目なら、この左手があります…!」
「で、でも……!」
イポーリトはオルティスを護るようにして、彼の前に立ちはだかった。
しかし、そのような皇子を瞬時に己の背後に匿(かくま)い、頑とした厳しい眼光でオルティスが言う。
「わたしのことより、皇子、御身のことを!!」
彼は衣服を引きちぎって素早く己の腕を止血すると、左に握った半月刀を手に馴染ませるかのようにビュッと強く振り切った。
とはいえ、その目元はわななくように痙攣し、どれほど平静を装っていようとも、実際には只ならぬ苦痛に耐えていることは明らかだった。
額からは脂汗が多量に噴出して滝のように伝い落ち、息遣いは今までとは別人のように荒く乱れ、止血した布もみるみる血の色に染まっていく。
負傷した傷口が、あまりに大きく、深いのだ。
先刻、もろに傷口を目の当たりにしたイポーリトには、オルティスがそこに立っていることすら信じ難かった。

「オルティス…!!」
悲痛な声を上げるイポーリトをよそに、いつしか辺りには、先ほど到着した敵の援軍と思しき兵たちが乱入してきており、まだ血痕や戦塵に染まっていない真新しい甲冑や軍服を、艶(なま)めく月光の下で照り返している。
隘路にごった返す夜間の戦場では敵の援軍の数を把握しようにも叶わず、ただ、それらの新参の兵たちの溢れるように漲る力ばかりが伝わってくる。
対するインカ兵は、体力も精神力も限界に達しようとしていた。
先程まで鬼神のような戦いぶりを見せていたオルティスさえも、利き腕を失った今、不慣れな左手で、しかも深々と身を斬り裂かれた常軌を逸する苦悶の中、見るに耐えぬ苦戦を強いられている。
そこに、さらに無数の敵兵たちが、大蟻の群れさながらに続々と群がっていく。
その瞬間、イポーリトの中で、何かが音を立てて激しくブチ切れた。
「やめ…ろ……」
うわ言のように呻き、血糊と塵と汗と涙とですっかり判別不能になった顔を、手の甲で荒々しく拭った。
「オルティスからも…皆からも…離れろ…!」
その眼が、熱せられた鉄弾のように燃え上がる――「消えろ――!!!」
彼は山の斜面に立った爪先に体重を掛けてバランスを取り直すと、サーベルをグッと胸元で斜(はす)に構えた。
と見るや、オルティスに群がる敵兵たちの中に、神速のスピードで斬り込んで行く。
「皇子……――!」
一瞬、オルティスの声が、遥か遠くで切れ切れに聴こえた気がした。
だが、それも、己の周りで反響する別の音によって、たちまち霧のように掻き消える。
剣の唸り、それが肉を断ち切り、骨に食い込む音――!!
それらが耳の奥で殷々と反響し、完全に無我になった心は、それが己の剣の放つ音であることさえ、もはやイポーリトには認識できなかった。

その間にも、皇子のサーベルは、敵兵の甲冑の隙間から相手の腋を貫いていく。
次の瞬間には、思い切りサーベルを相手の体から引き抜き、その重い亡骸を、襲いくる敵兵たちに向かってドサッと荒々しく投げ放った。
チラリと目の下を掠める己の腕は、剣の柄から手首までベットリと血糊がこびり付いて肘まで滴り、まるで黒いペンキを流したようだ。
しかし、そのような状態にも、今は何も感じなかった。
もはや、恐怖も、不安も、悲しみも、感情の何もかもが消滅してしまったかのような、不気味に澄み切った感覚だった。
ただ、胸の奥深くで、マグマが噴出し炸裂するかのごとく激しい何かが、猛烈な勢いで轟々と燃えている感覚だけがある。
もう、ベルムデスや手負いのオルティスが、どこにいるのかさえも分からない。
激烈な動きの連続に胸を波打たせ、髪振り乱して、今も狂ったように剣を振るいながらも、イポーリトの意識は次第にぼやけて取り止めがなくなっていく。
霞みゆく意識の中で、それでもなお戦い続ける彼の喉が、いつしか血を吐きながら咆哮を上げていた。
「みんな、負けるな!!
最後まで、絶対に諦めるな!!
絶対に、絶対に、希望を捨てるなあ――!!!」

同じ頃、本陣では、ついに敵将ガルベス大佐と彼の配下の兵たちに侵攻を許してしまったミカエラたちもまた、厳しい戦いを強いられていた。
戦闘経験の薄い義勇兵たちが大半を占めている本陣では、必死の抵抗も虚しく、多くの義勇兵たちが次々と敵の手に討たれていく。
このような時のために備えていた秘密の地下壕深くに幼い二人の皇子マリアノとフェルナンドを匿うと、ミカエラや専門兵たちは、まだ生き延びている義勇兵たちを庇いながら、死に物狂いの戦闘を展開していた。
ここでも戦況は既に生々しい白兵戦の様相を呈しており、敵味方入り乱れ合いながらの激しい乱戦となっていた。
整然と並んでいたはずの天幕は、敵の手で無残に斬り払われ、破壊され、蹂躙されていく。
それでも、さらにインカ兵たちが身を隠す遮蔽物を取り払い、完全に炙り出すために、ガルベスによって火をかけられた本陣は、今や炎の海と化していた。
その業火の中で、鋼の打ち合う音と阿鼻叫喚が嵐のように渦巻いている。

それでもなお、決死の覚悟で果敢に立ち向かい来るミカエラ軍の専門兵や義勇兵たち、さらには本陣の援護に駆けつけたインカ軍主力部隊の兵たちに対する迎撃に追われ、本陣のガルベス軍も、決して予断のならぬ状態にかわりはなかった。
ガルベスは、その魔人のような豪腕で、捨て身で立ち向かい来る義勇兵たちを容赦無く斬り伏せていく。
「ミカエラ――!!
どこに隠れている?!
これ以上の犠牲を出したくなくば、今すぐに投降しろ!!」
血走った眼を剥いてミカエラを探し回っていたガルベスが、燃え崩れゆくひときわ大きな天幕の傍に差し掛かった時、どこからともなく鋭い女性の声が響き渡ってきた。
「隠れなどしない!!」
不意に、緋色に燃え盛る炎の向こうに、長身の女性のシルエットが浮かび上がった。
「ミカエラ……!」
そのミカエラは、逆巻く炎を自身のオーラのごとく身に纏(まつ)わらせ、とても女性の手に負えるものとは思えぬ重厚な長剣をガッチリと握り締め、真っ直ぐに己の方へと歩み来る。

黄金色の火の粉が降りかかる女神のような美貌――しかし、今は、見るものを射殺すほどの険しく冷徹な表情が浮かんでいる。
「そなたが、ガルベス大佐か。
我らの本陣を、尊い兵たちの命を、よくもその汚らわしい土足で踏みにじってくれたものよ。
その行ない、そなたの身をもって贖(あがな)ってもらおうか!」
そう言って長剣を身構えたミカエラに、ガルベスも口の端を吊り上げた。
「ほお、面白い。
このわたしと勝負をしようというのかね」
一方、暫しの距離を隔てた炎の向こうからは、ミカエラの護衛兵たちが悲痛な声を張り上げている。
敵の勢いに押されて、こちらに辿り着けないでいるのだ。
だが、それはガルベス配下の兵たちにとっても、同じだった。
彼らの精兵たちが互いに激しくぶつかり合っている間にも、ミカエラとガルベスは相手を睨み据えたまま、早くも戦いの間合いを読み始めている。
ミカエラが己の長剣を目の高さまで挙げていくと、その刃渡りいっぱいに周囲の炎が照り返し、まるで剣が燃え上がっているかのような赤銅色の光を放った。
と見るや、次の瞬間には、二つの剣が鋭く唸って、ガシンッ!!と激しく打ち合った。
相手の剣から伝わる強度の重量感から、この男の異様な腕力を、幅広い筋肉質の体から繰り出される怪力を、その最初の一撃で、ミカエラは既に生々しく感じ取っていた。
(…――っつ!)
予想以上の相手の怪力に、険しい彼女の目元がいっそう鋭くそびやかされる。

ガッチリと結び合った鋼の向こうから、そのような彼女の微かな反応さえも抜け目無く見て取りながら、ガルベスの炯々たる眼光が、さらにギラツキを強めた。
しかし、ミカエラは、力のみに頼らぬ鞭のようなしなやかな筋肉の動きで、相手の剣を勢いよく弾き返す。
だが、距離を取ったのも束の間、再び双方の白刃が激しく打ち合った。
舞い飛ぶ火の粉の中で、二人の剣がさらに眩い火花を散らす。
ガシーン、ガシーン、ガシーン!!
厚い鋼が業火を裂いて相手のそれを叩きつけ、幾度と無く交錯した。
また受けかわし、今一度、距離を計りながら、互いにつけ入る隙を見出そうと回り込む。
ガルベスは、何としてもミカエラに斬りかからんとするが、彼にとっても、予想以上に俊敏な彼女の動きの前に、その機を掴めない。
他方、ミカエラも、相手の爆発的な力をかわしながら、一瞬の隙を突かんと狙い定めているが、全く攻撃の手の緩まぬ敵将の前で、彼女もまた攻めあぐんでいた。
全身総毛立たせ、修羅の形相で睨み合う両者を、灼熱の炎が轟々と押し包んでいく。

身を焼き焦がす熱気と激しい動きとによる体熱の高まりで、二人の全身には無数の汗が噴き出した。
その上、一呼吸ごとに高熱を帯びた空気で充満していく肺は、内側から焼けつくような疼きを与えてくる。
ガルベスの人間離れした剛腕と、ミカエラの並外れた敏捷でしなやかな動きと、互いに譲らぬ苛烈な攻防戦の中で、二人以外の一切のものが渦巻く火の壁の中へ退いていくかのようにさえ思われた。
が、その時、炎の向こうから、ガルベスの副官ナダルのものと思われる混乱した叫び声が、けたたましく響き渡ってきた。
「大佐!!
我が軍の兵の様子が変です!!」
副官の突然の叫びにガルベスの意識が微かにぶれた瞬間、彼の剣に絡んでいたミカエラの剣が、鋭い唸り音と共に大きく後方に引いた。
と思いきや、相手の両眼めがけて、電光石火のごとく突き込んでいく。

「――!!」
しかし、驚異的に鋭敏な運動神経で、ガルベスは自らの顔を反らすと、ミカエラの突きを間一髪のところでかわした。
剣が擦れ、彼の鼻先から真紅の血飛沫が弾け飛ぶ。
まさかのところでよけられ、今度は、逆にミカエラが、僅かにその身をよろめかせた。
その一瞬を逃さず、敵将の鉄棒のような腕が彼女を体ごと捕らえ、その手にある剣を蹴り飛ばした。
と同時に、彼女を地に引き倒し、その喉元に己の剣を押し当てる。
燃え盛る炎を背に、どす黒い影と化した男の巨躯が、ついに捕らえた獲物に獰猛に覆い被さった。
ガルベスが鬼のような形相で凄む。
「勝負はあった。
降伏しろ!!
押し倒された状態のまま、ミカエラは険しい表情で相手を睨み上げていたが、やがて口惜しげに長い睫毛を伏せた。
それでも決して力を緩めることなく、ガルベスは予断無くミカエラを押さえ込んでいる。
そうしながら、相手が降伏を認める瞬間を待った。
「ガルベス大佐…」
やがてミカエラの形良い唇が、吐息交じりの擦れ声を漏らした。
「そのように力を込めては痛いですわ……。
このような暴力的なことは…もうお仕舞いにして、二人きりでお話でもしませんこと?」
そう囁きながら、熱情を帯びた潤んだ瞳をゆるやかに見開き、ガルベスを上目遣いに熱っぽく見つめた。
そして、彼の手の中で、そのしなやかな身をよじらせ、苦しげに瞼を震わせる。
「ば、馬鹿な…何をこの期に及んで…!」
いきり立って答えた己の声音が、不覚にも上擦っているさまに、ガルベスは自らに肝を冷やした。

かたやミカエラは、そんな相手の気を引くように艶(なま)めかしく肢体を反らし、乱れた長い黒髪を波立たせながら、イヤイヤをするように頭を振った。
その動きに合わせ、胸甲に覆われていても明らかに豊満さの分かる胸の膨らみが、彼女の上腕を押さえ込んでいるガルベスの指先に、いやがうえにも生々しく押しつけられていく。
さすがにガルベスもそのままの状態に堪えきれなくなったのか、胸の押しつけられた己の指をずらそうとした時、微かにその腕力が緩んだ。
その一瞬の隙に、ミカエラは素早く口を使って、首から提げていた革紐を胸甲の襟元から引っ張り出した。
それは革紐の先に小袋を結びつけたペンダント状のもので、今しがた首を振りながら、その紐を胸元から首の上方まで引き上げていたのだった。
そして、引き出した紐の先端から小袋を歯で引きちぎり、相手の顔めがけて思い切り投げつけた。
途端に、小袋はガルベスの顔面中央で炸裂し、袋の中に入っていた透明な液体が、彼の顔や髪に弾け飛んだ。
目の中まで液体が飛び散ったガルベスが、「ギャッ!!」と獣のように叫んで、火のような激痛に、思わず片手で顔を覆う。
その瞬間、ミカエラを拘束していた敵将の剣先が、彼女の体から離れた。
(今――!!)
ミカエラはすかさず身を翻し、自由になった片腕を伸ばして衣服の下の大腿部に結んでいた小刀を引き抜くと、まだ執拗に己を押さえ込んでいる男のもう片方の手に容赦無くそれを突き立てた。
「グワッ!!」
ガルベスが迂闊にも悲痛な叫び声を上げた時には、ミカエラの全身は完全に相手の腕から自由になっていた。
間髪入れず、瞬時に拾い上げたミカエラの長剣が、鋭い唸り音と共に敵将の頭上に迫る。
ガンッ!!――即座に受け留めたガルベスの剣から伝わる激しい振動が、ミカエラの総身を電流のように駆け抜けた。
血走った目を剥いて立ち上がりざま、ガルベスは凄まじい勢いでミカエラの剣を払いのける。
相手の怪力に弾き飛ばされそうになった体を、彼女は足に力を込めて、懸命に踏みとどまった。
そうしながら、冷徹な面差しで相手を見据え、冷ややかに言う。
「下手に動けば辺りの火が移り、そなたの頭は瞬く間に火だるまになる」
「…――やはり油か。
姑息(こそく)な真似を……!」
ガルベスは顔面や髪からヌラつく液体を滴らせたまま、憤怒と憎悪に猛り狂った眼を呪わしげにギラつかせる。
そうしながら、太い片腕を顔の前にかざし、舞い飛ぶ火の粉を苛立たしげに払いのけた。
その手の甲は、今しがたミカエラに突き立てられた小刀によってザックリと割れており、そこから夥しい血が溢れ出している。

一方、ミカエラは、そのような敵将の姿を、能面のごとく無感情な表情で睥睨した。
「ガルベス大佐。
今頃は、そなたの鎧の奥まで油が滲み込んでおろう。
ひとたび火がかかれば、もはや顔や頭だけでは済まされまい。
だが、所詮は、そなた自身の放った火だ。
たとえ、そなたの全身が鎧の中で蒸し焼きになろうとも、それに焼かれるならば悔いも無かろう」
そう低く言いながら、いつの間に拾い上げたのか、小刀の先端に突き刺した燃え盛る木片を、相手の眼前にゆっくりと掲げ上げていく。
炎に包まれた木片を相手の顔に近づけながら、ミカエラの瞳が酷薄な閃光を放つ。
「ガルベス大佐、即刻、そなたの全兵を当地から退かせよ!!
分かっておろう?
これは、ただの脅しではない。
そなたが否やと言えば、即座にこの火をそなたに投げかける。
そなたが退却を命ぜずとも、将を失えば、そなたの兵たちも少しは大人しくなろう」
だが、ガルベスは、そのようなミカエラの言葉を、「フッ」と鼻先で一蹴した。
脂ぎった髪を逆立たせ、激昂の極みに達したその形相は、怪物とも魔物ともつかぬ凄まじいものと化している。
その表情には、今、不気味な笑みさえ浮かび上がる。
「これは笑止――!
このわたしが、このようなくだらぬ脅しに乗せられると本気で思っているのかね。
そもそも、これしきの油で、このわたしが焼き尽くせるなどとは笑わせる!
それに、もしおまえの目論み通り、首尾よくわたしに火が回れば、その時はおまえもただでは済まされぬ。
火だるまになった体ごと、おまえに体当たりしてくれるわ!!」

周囲では、先にも増して轟々と激しく炎が燃え滾っている。
それらの厚い緋色の壁が、まるで二人を元の世界から完全に切り離してしまったかのように、辺りに人の気配は皆無だった。
実は、それもそのはずで、1対1の戦闘に持ち込みながら、ミカエラは意図的に本陣の奥深くへとガルベスを誘い込んでいたのだった。
配下の精兵から彼を引き離し、単独にした上で、脅しを用いてでも降伏を説得するつもりであった。
だが、死をも恐れぬ本来の豪胆さゆえなのか、あるいは、憤激のあまり理性の箍がはずれているのか、いずれにしろ命惜しみをすることの全く無い敵将を前に、ミカエラは二人きりに持ち込んだことを悔やみ始めていた。
もしガルベスに火を放てば、恐らく彼の言葉通り、本気で己を巻き添えにするつもりであろう。
自分までもが無残に焼死したなどとなれば、今しも壊滅寸前の危機にある当地のインカ兵たちは、どうなってしまうであろう……?!
ミカエラの密かな怯みを見透かしているかのように、ガルベスは冷酷なせせら笑いを口の端に浮かべながら、一歩、一歩、彼女の方へと迫り来る。
無慈悲な、瞬きひとつせぬ男の目は、猛烈な殺気を帯びている。
かたやミカエラは、燃える木片を手にしたまま、ジリジリと後退していく。
次第に断崖の絶壁際まで追い詰められていく己の不甲斐無さに臍(ほぞ)を噛みながら、彼女の頭は、懸命に打つべき手を探し続けた。
だが、この世のものとは思えぬ凄まじい形相で、狂気を孕んだ眼光を炯々とさせ、油と脂汗を照らつかせながら迫り来るガルベスの禍々しい「気」に呑まれ、ミカエラの思考はその力を吸い取られていく。

他方、ガルベスの手には、いつしか小銃がしっかりと握られている。
「もう、お遊びはここまでだ。
せいぜい命だけは助けて、アレッチェ様の手土産にと思っていたが、こうなっては、そのようなことも言ってはおられまい」
地底から湧き出すような低く凄んだ声で言いながら、至近距離にもかかわらず、その銃を、いかにも手馴れた手つきで、じっくり着実に、ミカエラの方へと身構えていく。
しかし、その時だった。
銃を構えるガルベスの背後から、彼の頭や胴体に、ドゴッ、と重い音を発して、鋭い石片が勢い良くぶち当たってきた。
「なっ――?!」
銃を構えたまま、いきり立った眼で、ガルベスが半顔だけ後方を振り向く。
ミカエラも、すかさず彼の後方へと視線を馳せ、それから驚愕して目を見張った。
視線の先には、暫しの距離を隔てて、険しい目で敵将を睨み据えて立つ二人の幼い皇子たち――次男マリアノと末子フェルナンドがいたのだ。
「母上から離れろ!!」
決然とした声でマリアノが叫ぶ。
その手には、インカ伝統の武器、オンダ(紐に通した石を振り回して投げ放つ投石器)が力強く握られている。
そんなマリアノの横では、まだ年端もいかぬフェルナンドが、やはり毅然とオンダを構え、兄にも負けず劣らず険しい目で敵将を見据えている。
対照的に、ミカエラは真っ青になった。
「出てきてはいけないと、あれほど言っておいたのに……!!」
恐らく、マリアノたちを匿っていた兵たちが戦闘に巻き込まれ、隠れていた二人も、戦況や母の安否を案じて飛び出してきてしまったのであろう。

一方、ガルベスは、いよいよ狂気じみた高笑いをしながら、ミカエラと皇子たちを交互に見渡した。
「これは傑作だ!!
おかげで、ガキどもを探し回る手間が省けたというものだ。
それに、これで、アレッチェ様への恰好の手土産も確保できた。
ミカエラ、おまえには、心置きなく消えてもらうことができる」
そう荒々しく吼え上げ、ミカエラの胸甲に小銃の先端をあてがい、銃口で彼女の体を強引に押しながら絶壁際へと追い込んでいく。
しかも、彼女が追い詰められているその場所は、主戦場となっている隘路に繋がる断崖壁とは対極側にあり、その足元は、遥か下方の山麓から切り立つ、目も眩むような断崖絶壁となっている。
ミカエラは、背後に残された僅かな足場を懸命に推し量りながらも、幼い息子たちの方へハラハラと意識を馳せずにはいられない。
(ああ……なんてことに…!!)
対するマリアノとフェルナンドは、さらにこちらへと距離を詰めながら、オンダに棘ばった石をつがえ、ガルベスめがけて投げ放った。
「母上から離れろ!!!」
インカのオンダは、鍛えられた兵士が投げつければ、鋼鉄の鎧さえも突き破るほどの強烈な破壊力を持つ。
まだ幼いマリアノたちにはそのような力は無いものの、それでも母を守ろうと無我夢中で投げ放つ二人の石は、見事なほどに相手の全身に次々と命中し、その鎧をボコボコに叩きのめしていく。
苛立たしげに振り向きざま、ガルベスの銃口から放たれた銃弾が、マリアノの頭スレスレを掠め飛んだ。
ビクリと身を固めたマリアノに、ガルベスの鬼のような怒声が飛ぶ。
「おまえも殺されたいか!?」
がなりつけながらも、すぐにミカエラに向き直り、彼女の体に再び銃を突きつける。

その時、突如、ミカエラの手がその銃身をグッと捕えた。
自ら銃口を己の胸甲に押し付けたままの形に固定するかのように、彼女の手は、高熱を帯びた銃身を強く握り締めていく。
と同時に、敵将の肩越しに、彼女の声が厳然と響き渡った。
「マリアノ、フェルナンド!!
母を思ってくれるそなたたちの気持ち、この身にしかと染み入りました。
なれど、そなたたちは、自由の身のまま、何としても生き延びねばならぬ!
残された兵たちのためにも、民のためにも!!
さあ、即刻、そこから立ち去るのです!
この者は、今、火に弱い!!
そなたたちは、できるだけ炎の傍を、火の粉の中をかいくぐって逃げよ!!」
「黙れ!!」
ミカエラが堅く押さえ込んでいる銃を、ガルベスの巨大な手が、引き千切るようにもぎ取った。
その勢いの激しさに、彼女のもう片手に握られていた燃える木片が小刀ごと地に転がり落ち、そのまま果てしない断崖下へと呑み込まれていった。
ガルベスの両眼が、カッと、獰猛な光を放つ。
「さらばだ、ミカエラ」
が、ガルベスの言葉に重なって、まだ少女のように澄んだフェルナンドの声が、高らかに響き渡ってきた。
「あれは?!
母上、あれは何?!
兄上!!
見て、山の下を!!!」
不意のことに、しかしながら、フェルナンドの声音のあまりに驚嘆と興奮に満ちたさまに、ミカエラもガルベスも、思わず、断崖下に広がる下界へと視線を馳せた。
もし明るい陽光の降り注ぐ昼間であるならば、そこからは、山麓に広がる緑と茶の縞目模様を織り成す平原の彼方まで、遥々と見晴るかすことができる。
だが、夜間ともなると、下界は深海に呑まれたように深い闇の中に沈んでしまう。
見えるとしても、せいぜい遠い麓の集落に転々と点る、民家の儚げな灯りぐらいのものである。
しかし、今、己の視界に飛び込んできた下界の光景に、ミカエラの目は張り裂けぬばかりに見開かれた。
(え?!
あれは――?!)
その瞳が信じられぬ、という激しい驚愕と共に、強い歓喜に恍惚と大きく輝いた。
下界のその信じがたい光景は、夜の闇の中でもハッキリと見え、いや、闇の中だからこそ、あんなにも鮮烈に眩く見えるのだ。

他方、ガルベスは、ミカエラを凌ぐ驚愕の表情で、ギョッと険しく目を剥き上げた。
「な、なんだ、あれは?!
まさか、あんな…ありえん……!!」
愕然とした彼の意識がそちらにそれた、その一瞬の隙だった。
ミカエラの雌獣のようにしなやかな体が、すかさず相手の側面へと滑り込む。
と同時に、横合いから突き出された彼女の両腕が、敵将の巨体を、断崖の向こうの空間へ思い切り突き放った。
「グァ…!!!」
ガルベスが何か叫び声を上げたが、その時には、足場を失った彼の体は、断崖下の遥か下界に向けて真っ逆さまに吸い込まれていくところだった。
ウォ―――・・・虚空を切り裂く絶叫が、断崖絶壁に幾重にも反響しながら、気の遠くなるような下方へと、みるみる遠のいていく。
そして、ほどなく、果てしない深淵の彼方に、その姿と共に完全に消え去っていった。
かくして、ミカエラとガルベスが一つの決着を見た頃、イポーリトたちの状況はどうなっていたであろうか。
敵方の援軍が到着し、己を強力に護ってくれていたオルティスも負傷した中、その命も風前の灯と思われたイポーリトであったが、幸運にも、まだ彼はその命の灯をこの世に繋いでいた。
ベルムデスの庇護が健在であったこと、そして、我武者羅に戦い続ける皇子の姿に感化されたインカ兵たちが最後の力を振り絞って死に物狂いで奮戦したことなどが、功を奏した面もあっただろう。
しかし、それ以上に、イポーリトやインカ軍が未だ壊滅せずにすんでいたのには、むしろスペイン軍側の問題が大きかった。
というのは、スペイン兵たちに、ある異変が生じていたのだ。

まともな明かりと言えば、点在する松明の火や仄かな月光ぐらいで、その上、狭い隘路での乱戦状態に陥っていたために、一体、何がどうなっているのか、イポーリトには全く掴めていなかった。
(だけど、明らかに敵の勢力が弱まっている……!)
理由は分からなかったが、これまでのように圧倒的な力で押しまくられる感覚が薄らいでいることを、その身をもってハッキリと実感していた。
先刻までの、息もつかせぬほどに次々と己に襲い掛かっていた敵の刃は、その勢いを確実に失っている。
(なぜだ?!
敵は援軍さえ得たはずじゃないか!!)
今ではもう、イポーリトの姿は、完全に頭頂から爪先まで赤黒いペンキ桶を被ったも同然の、全身血みどろのありさまであった。
その状態のまま、彼は真相を探ろうと、血糊で固まった前髪の隙間から鋭い夜目を光らせる。
それと同時に、いかに勢力は弱まっているとはいえ、まだ、いつ襲いかかり来るか分からぬ敵兵への注意を360度全方向に怠らない。
そうしながらも、自分の心の呟きを反芻して、ハッと息を詰めた。
(援軍…!
そうだ…あの援軍が到着してからじゃないのか?
援軍が来て、最初は勢いを増したように思えた敵軍だったが…。
でも、敵軍の何かが、だんだんおかしくなってきたのも、あの後からじゃ……?)
皇子の傍で長剣と笏杖を振るうベルムデスもまた、状況を掴もうとしているのであろう。
さすがの彼も、長時間の激しい動きの連続による疲労を横顔に滲ませてはいたが、それでも、周囲を隙無く見渡す鷲のように鋭利な眼光は、今もなお健在である。
すっかり離れ離れになってしまった手負いのオルティスも、必ずやこの戦場のどこかで生き延びていて、この得体の知れぬ異変の臭いを嗅ぎ取っているに違いない。
強く念ずる思いで、イポーリトはそう胸の中で噛み締めた。
その時、不意に、背後に強い殺気が迫った。
イポーリトは即座に身を翻し、襲い来る敵兵の剣を受けかわした。
それと共に、戦さの冒頭の頃とはまるで別人のように、要を得た身のこなしで相手の急所に斬りかかっていく。
すると、まだ、まともな勝負が始まってさえいないのに、敵兵は咄嗟に大きく跳びすさって身を引くと、まるで何かに怯えているかのようにオズオズと後ずさりだした。
(え…?!)
イポーリトの方が驚いて、剣を斜に構えたまま、鎧の陰から覗く相手の顔を見上げた。
月光に鈍く反射する敵兵の目は、怯えと怒りと混乱が激しくない交ぜになっている。
それは眼前のイポーリトに向ける感情というよりも、何かもっと大きな恐怖――いや、むしろ狂気のようなものか?――に支配されてしまっているかのようにさえ見えた。
それが何なのか、イポーリトの目が必死で探ろうと、さらに一歩を踏み込んだ時、敵兵は「ギャッ!!」と唐突な叫びを上げて身を翻し、もろに背後を晒したまま、ワッと逃げ出した。
まるで怯えた子どものように逃げ去る相手の背中を呆然と見やりながら、イポーリトは血の味の混ざった固唾を呑みくだす。
だが、次の瞬間、彼はさらに信じられぬ光景を目の当たりにした。

イポーリトの目の前から逃げ去ったスペイン兵の前に、突如、鋼鉄の鎧に身を包んだ別のスペイン兵が立ちはだかったかと思いきや、眼前に走り込んできたその同族の兵をいきなり斬り付けたのだ。
(なっ…――?!)
イポーリトは激しいショックで、愕然と身を強張らせる。
(同士討ち?!
ど、どうなってるんだ?!)
頭が真白になるほどの強度の混乱を覚えながら辺りの闇に必死で夜目を凝らせば、なんと、スペイン兵たちは、おぞましくも、戦場の随所で互いを斬り付け合っているではないか。
敵兵同士のこととはいえ、あまりの衝撃と戦慄にイポーリトの背筋は凍りついた。
その虚を突くかのように、再び彼の背後から、剣を上段に振りかぶった新たな敵兵が、猛烈な勢いで襲いかかってきた。
(しまった……!!)
敵軍の異常に完全に気を取られていた彼が己の危機を察知した時には、もう敵兵は、覆い被さるほどの至近距離まで詰めていた。
よもや――!と思われたその瞬間、不意に、横合いから何者かの重厚な剣が繰り出され、月光を反射して鋭く一閃した。
と同時に、皇子に押し迫っていた敵兵の剣を火花と共に、ガッ、と受け留め、鍔でひねり込むようにして相手の剣を猛然と弾き飛ばした。
イポーリトとスペイン兵との間に割り入ってきたその何者かが、今度は目にも留まらぬ敏捷さで銃を引き抜き、今、剣を弾き飛ばしたばかりの兵めがけてピタリと狙い定める。
途端に、スペイン兵はギャアと叫んで、弾かれた己の剣を拾うことさえ忘れて、脱兎のごとく逃げ去っていった。
その後ろ姿に向かって今にも引き金を引かんとしている眼前の人物を見上げて、イポーリトはさらに大きく息を呑んだ。
己を助けてくれたその人も、厳つい鋼の甲冑に身を包んだスペイン兵だったのだ!!
「ま、待って……!!」
イポーリトの逼迫した声が、夜の大気を震わせる。
「どうして自分の味方を撃とうとするの?!
どうして…どうして敵のあなたが、僕を助けてくれたんです?!」
絡まった混乱の糸を解こうと必死で、相手がスペイン兵であることも忘れて、イポーリトは矢継ぎ早に尋ねずにはいられない。
すると、鎧の人物は眼前の少年を暫し無言で見下ろしていたが、やがて、顔面部のマスクをずらし、素顔を覗かせた。
「あ…――!!」
驚愕するイポーリトの口元が、声にならぬ声を上げる。
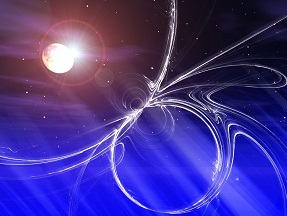
「シモン殿……!!!」
信じられぬという眼で穴の空くほど己の顔を凝視している少年の全身を、シモンもまた、くまなく見渡した後、フッと吐息を漏らした。
「間に合って良かった」
短い一言だったが、その声音には深い安堵の響きが宿っている。
一方、イポーリトは、ますます大きな混乱に嵌り込んだまま、目も口も呆然と開け放った状態で身動きひとつできずにいる。
口をパクパクさせながら言葉にならぬ声を放っている彼の姿を、今一度、シモンはひとしきり見渡した。
生々しい血肉のこびり付いたサーベルを握り締めて立ち尽くす皇子の驚嘆した眼が、辛うじて月光に照り映えてはいるものの、それ以外の赤黒く染まっりきった全身は、まるで彼自身が肉塊と化してしまったかのようで、正視に堪えぬものだった。
もし己の姿を鏡に映してみようものなら、イポーリト自身が卒倒してしまうかもしれない。
シモンは口元からまた息を漏らし、それから、微かにその目を細めた。
「大変な戦いだったな。
良く生き延びたじゃないか」
対するイポーリトは、いよいよ身をそびやかせ、大きく頭(かぶり)を振った。
「――ど、どうして?!!
どうしてあなたがここにいるの?!
あなたはリマに行ったんじゃなかったの?!」

イポーリトは興奮の止まらぬ全身を半ば震わせながら、あっ、もしや!!――と、続けて叫んだ。
「もしやスペイン軍の援軍って、あなたたちの軍だったの……?!」
シモンは軽く頷き、身に纏った鋼の鎧を、カンッ、と指先で小突いた。
「まあ、そういうことだ。
君たちを援護するために、敢えてスペイン軍の援軍になりすました、というのが正確なところだが。
どうだ?
スペイン軍の兵と見紛うような、なかなかの出で立ちであろう?」
言葉の発せぬイポーリトの様子に頓着することもなく、シモンがさらに続けていく。
「鎧や火器も、スペイン人の我々なら、それなりのルートに相応の金を積めば手に入れられる。
相手の目を欺くために敵軍の軍旗や紋章の類を取り揃えておくのは良くある手だが、まさか、このような場所で役に立とうとはな」
そう言って軽く鋼鉄の肩を竦めた。
場所柄にもかかわらず、その相変わらずの飄々たる調子さえ、今となってはあまりに懐かしい。
そんなシモンの言葉が耳にも心にも沁み込むうちに、突如、イポーリトの中に激しい感情が爆発的に突き上げてきた。
「でも…ってか、だから、どうして?!
僕らの巻き添えになって死ぬのは嫌だって、あんなにハッキリ言ってたじゃないか!!
なのに、なんで、なんで戻ってきたの?!」
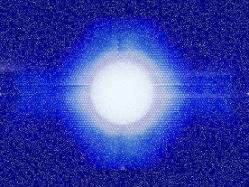
己に噛み付くように叫び立てるイポーリトをいなしながら、シモンがまた淡々と答える。
「この本陣が陥落し、君たちが人質にでもされて、トゥパク・アマル殿の計画が頓挫しては、我々にとっても元も子もないことだ。
リマ戦は重要だが、まず、この本陣を防衛することが、当然ながら優先だ」
「それじゃ、あなたは、援軍として戻ってきてくれるつもりが初めからあったってこと?!」
「もちろんだ」
相変わらず飄々と答えるシモンの調子に、イポーリトの昂ぶった感情はいよいよ炸裂する。
「じゃっ、なんで、最初からそう言ってくれなかったんだよ?!
戻ってくるって言ってくれれば、母上も、僕たちも、もっと落ち着いて事態に対処できたのに!!」
「だから、言わなかったのだ」
「え?!」
本気で噛み付きそうなイポーリトの方へ、また鎧の肩を軽く竦めて、シモンが答える。
「君たちはひどく劣勢な上、インカ側の援軍も期待できず、退路も絶たれて、普通に考えれば勝機など殆ど望めぬ状況だった。
だが、逆に見れば、かなり上手いこと背水の陣に置かれていたとも言える。
ならば、その状況を生かさぬ手は無い。
徹底的に追い詰められることで、持てる以上の力が発揮されれば――あるいは、不可能と思われた僅かな勝機も生まれるかもしれない。
そのためには、たかだか千にも満たぬわたしの援軍を連れて来るなどと言って期待を持たせては、むしろ、いらぬ水を差すだけだと思ったのだ。
実際、援軍も期待できぬと腹を括ったからこそ、かえって君たちは、ここまで死に物狂いで奮戦できたんじゃないのか?」
思いのほか真面目な声音のシモンの言葉に、吠え立てていたイポーリトも、一瞬、おとなしくなった。
「え…じゃ、あなたは僕らが力を尽くせるよう、敢えて立ち去った振りをしたって言うの?」
「徹底的に窮地に追い込まれた方が、かえって実力以上の力が引き出されるものだ」
そう言ってシモンは皇子に一瞥を投げ、「身をもって、君はそれを体験したんじゃないのか?」と、僅かに口の端を上げた。
そのシモンの態度が、イポーリトの鎮まりかけた感情に、また火をつけた。
「あなたの言っていることは、みんな屁理屈だ!!」
またしても執拗に吠え掛かりだしたイポーリトを面倒くさそうにかわして、再びシモンが顔面のマスクを装着する。
「ともかく話は後だ。
まだ戦いの決着はついていないぞ!
この機に勝負を決めてしまわねば、今は混乱している敵兵たちも、すぐに正気を取り戻してしまうかもしれん」
そう言い置いて、剣と銃を携えて去りかけたシモンの腕を、真っ赤に染まった少年の手が強く捕らえた。
「待って!!
もう一つだけ教えて!!」

歩みを止めぬまま半顔だけ振り向いたシモンに、イポーリトが険しい表情で問う。
「スペイン兵たちが同士討ちを始めたのも、あなたのせいなの?!」
「わたしのせいという言われ方は心外だが、まあ、そういうことだ。
我らの軍も、知っての通り、まともに当たって功を奏するような数を備えてはいない。
だから、スペイン軍の援軍になりすまし、スペイン兵たちの中に紛れ込み、仲間と思わせておきながら唐突に攻撃をしかけたのだ。
味方と思われる者から裏切りの不意打ちをいきなり受ければ、たいがいの人間なら頭に血が上り、疑心暗鬼になって、果ては殺し合いに発展する。
ただでさえ極限状態にある戦場なら、なおさらのことだ。
もし援軍を装って現われた我々を疑う者がいようとも、殆ど同じ装いの我々を闇の中で見分けることは至難。
その上、君たちインカ兵の攻撃も相変わらず予断ならない。
そんな状況におかれたスペイン兵たちにとって、周り中全てが敵に思えてきても不思議はない。
大勢で一斉にその状態を誘発すれば、場は混乱して、あとは放置していても、彼ら自身で相討ちを続けてくれる」
「なんて…なんて残酷なことをするんだ…あなたは!!
いくら敵軍だからって、味方同士で殺し合いをさせるなんて……!!」

衝撃と憤激に昂ぶるあまり、その手にある剣をこちらに向かって突き込んできかねぬ勢いのイポーリトに、シモンは冷徹な視線を馳せ、それから低く言う。
「人間同士で殺し合う戦いなんて、大なり小なり、それと似たようなものじゃないのか?」
「…――!!」
「それに、こうでもしなければ、君たちは、今頃は敵に制圧されていただろうよ。
君たちは、当初の奇襲作戦もたいした効果を上げられなかった上、無策な乱戦を延々と続けているような状況に陥っていた。
そうともなれば、敵を内側から崩すしかあるまい」
「じゃっ…あなたは、初めからずっと僕らの戦いを見ていたってこと?!」
「わたしだって、斥候ぐらいは放つ。
戦況が分からなければ、援護の仕方だって決められないだろう」
再び無感情に語るシモンの前で絶句するイポーリトの目からは、いつしかドッと涙が噴き出していた。
激しい興奮と、昂ぶりと、憤りと、否それ以上に、深い安堵からだったかもしれない。
イポーリトは血染めの手で咄嗟に目元を覆って、バッと大きく顔をそらした。
(――見捨てずに戻ってきてくれた……!!!)
溢れ出す涙を止めようと必死で唇を噛み締めても、込み上げるものを止めることができない。

目を覆った指の隙間から滔々と滲み出す涙で頬の血を洗い流している少年の姿に、シモンもついに足を止めた。
そして、小刻みに震える相手の肩に鎧の手を添え、初めて真摯な声で囁く。
「その手でこの陣営を守ってみせると言っていた、あの時の君の言葉を君は守ったのだ」
いよいよ涙にむせぶイポーリトの肩を叩き、シモンが言う。
「だが、まだ終わっていない。
まだ泣くのは早いぞ。
一刻も早く決着をつけねば、正気を取り戻した敵軍に、今度は我らがまとめて一網打尽にされかねん」
その時、少し離れた場所で長剣を振るいながらも、こちらを見守っていたベルムデスとシモンの目が合った。
シモン殿、やはり戻ってきてくださったのですな――目元に皴を寄せて微笑むベルムデスの老練な面差しに、シモンも深く礼を返す。
それとほぼ同時に、隘路の断崖沿いで戦っていたインカ兵たちから、ドッ、と大きな歓声が湧き上がった。
「おい、見ろ!!
援軍だ!!!
今度こそ、我がインカ軍の援軍だぞ!!」
嵐のような歓喜と興奮に叫び合うインカ兵たちの方を、イポーリトも、シモンも、ベルムデスも、ハッと振り返る。
下界を見下ろす位置にいる兵たちは、山麓の方向を夢中で指差しながら、今にも舞い踊り出しそうな勢いだ。
「イポーリト様、ものすごい大軍です!!
どうか山の麓をご覧ください!!
これは…これは夢なんでしょうか?!」
兵たちの歓呼の叫びに急き立てられるようにして、泣き腫らした顔もそのままに、イポーリトは傍らの高台に一気に駆け上った。
そして、兵たちが笑顔を輝かせながら力強く指し示す遥かな下界を、大きく覗き込んだ。
(あれは――!?)

大きく見開かれた彼の漆黒の瞳の中に、山麓の平原に巨大な真紅の絨毯を広げたような炎の海が飛び込んだ。
目を凝らせば、それは夜闇を照らす無数の松明の光であった。
その松明を掲げた人々の大軍団が、山麓の平原を猛然とこちらに向かって進み来ているのだ。
遥か彼方の下界での様子のため個々の人々の姿までは見分けられないが、それがインカ側の大軍であることは一目で分かる。
遠く風に乗って響き来るのは、インカ兵たちの勇壮なケチュア語の雄叫びと、彼らが吹き鳴らす高らかな角笛の音だ!
しかも、煌々たる松明の波間の随所で七色に輝いて見えるのは、インカ軍を象徴する七色の御旗に違いない!!
一体、どれほどの兵がいるのだろう?――1万?2万?3万?いやもっとだろうか?!
どこからそのような大軍勢を集めることができたのか、ここにいる誰にも、想像すらつかなかった。
だが、それでも、強力な援軍がこちらに向かっている、その事実は揺るがしようがない。
イポーリトはもちろん、ベルムデスも、他のインカ兵たちの誰もが激しく胸を熱くして、その眩い光景に恍惚と釘づけられたまま、いつまでも目を離すことができなかった。
「父上…――!!」
皇子の頬を熱い涙が伝って流れた。

ふと下方から視線を感じて、そちらに目をやれば、幾ばくかの距離を隔てた戦場の一角で、オルティスが高台に立つ己を見上げている姿が、月光に照らされて浮き上がって見えた。
(オルティス!!
やっぱり生きていてくれた!!)
イポーリトは涙の乾かぬその顔に大きな笑みをつくって、勢い良くガッツポーズを送る。
オルティスも、あの精悍な笑顔を見せながら、健在な左手に握り締めた半月刀をかざして、皇子に力強く応えた。
とはいえ、その表情や動作とは裏腹に、青白い月光に浮かび上がるオルティスの顔は完全に血の気を失っており、今にもそこに崩おれそうだ。
さらに高台から彼の周囲をザッと見渡しただけでも、歓喜すべきはずのこの瞬間さえ、戦場の随所で数限り無い兵たちが瀕死の重態に身悶えているのだった。
イポーリトは再び険しい目になって、飛ぶようにして高台を駆け下りた。
そして、まだ身体の自由なインカ兵たちを見渡し、サーベルを振り上げ、渾身の力で雄叫びを上げる。
「さあ!!
みんな、下界の巨大な援軍も、もうすぐ戦いに加わってくれる!!
これからは、僕たちが圧倒的に優勢だ!
もう何も恐れるものはないぞ!
今こそ敵兵どもを完全に蹴散らそう!!
反撃だ――!!」
「オ――!!!」
皇子の檄に応えて、逞しいインカ兵たちの勇ましい鬨の声が山々に木霊する。
他方、息を吹き返したように強力な反撃を開始したインカ軍に対して、シモンの策謀によって、既に強度の混乱と憔悴の渦中にあったスペイン軍は、みるみるインカ軍の猛攻に押されていく。

その頃、同様に、ミカエラ率いる本陣のインカ兵たちもまた、山麓に現われたインカ側の援軍到来を知って猛烈な反撃に転じていた。
実は、敵将ガルベスによって断崖絶壁に追い詰められたミカエラが、あの時、遥か下方の山麓に見出したものこそ、このインカ軍の大援軍であった。
いずれにしろ、戦神が宿ったかのように強烈に攻め上げてくるインカ兵に対して、逆にスペイン兵たちは、追い討ちをかけるように彼らの大将ガルベスを失ったことを知らされ、その士気も統率もさらに崩れていく。
その上、山麓を馳せていたインカ軍の巨大な援軍は、この戦場に向かって早くも山を駆け登り始めているらしく、月夜の霊峰に響き渡る角笛の音やケチュア語の咆哮が、先ほどよりもずっと鮮明に迫って聞こえてくるのだった。
あの勢いならば、あの援軍は、そう遠からず、確実にこの戦場に到着することだろう。
ガルベスのいない今、当地のスペイン軍を統率する立場となった副官ナダルや彼の側近の将校たちは、強張った表情をさらに引きつらせた。
あのインカ側の大軍がここに乗り込んでくるまでに、この場にいるインカ兵を撃破し、ミカエラや皇子たちをひっ捕らえて、その上、無事に下山を果たすことができるのか?!
ナダルも、将校たちも、その可能性を必死に推し量ってみる。
だが、今となっては、それは非常に難儀なことに思われた。
しかも、同士討ちの混乱や戦慄、そして、迫り来るインカ軍の援軍に対する恐怖に耐えかねたスペイン兵たちの多くが、夜闇に乗じて戦線を離脱し始め、既に逃走を開始しているという有様であった。
かくして、ナダルたちは、苦渋の敗退を余儀なくされたのであった。

「退け、退け、退け――!!!」
逼迫した将校たちの号令がけたたましく響き渡る中、スペイン兵たちは、唯一の山道を登り来るインカ軍の援軍を避けるために、その道を引き返すこともままならず、道無き道を求めて、闇に覆われた獣道へと離散していった。
恐らく、追い討ちをかけるまでもなく、無数の野獣が目を光らせる急峻で危険極まりない夜の山林に彷徨い込んだ彼らが、無事に下山できる可能性は極めて薄かろう。
![]()
![]()
![]()